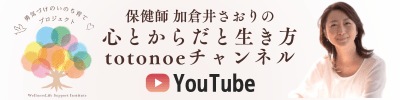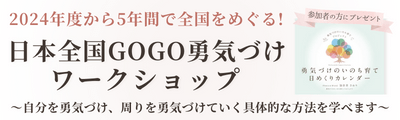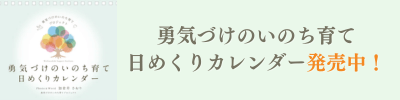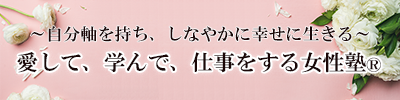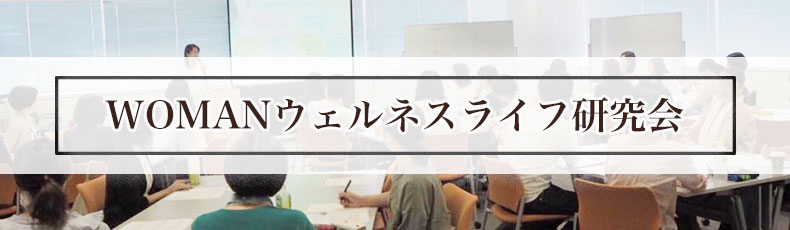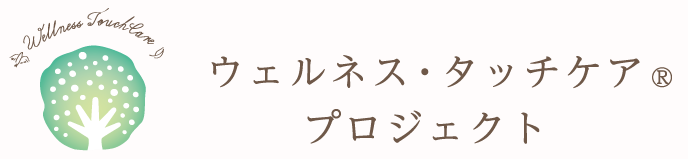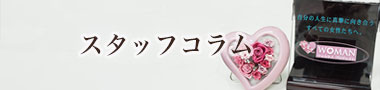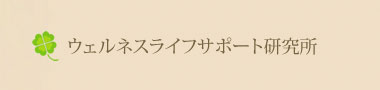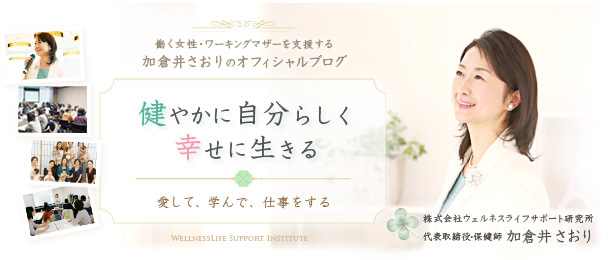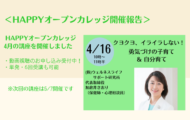第3回のテーマは「人生100年時代に考えたい女性の健康課題」
「人生100年時代」、日本の女性の2人に1人は90歳まで生きるといわれています。
そんな長寿社会に向けて、女性が「いま」そして「これから」を、イキイキと暮らしていくために、考えていくべき健康課題とは何でしょうか。
今回の研究会は、第1部は、産婦人科医の直林氏に「診察の現場」のケースをもとに、様々な世代の課題や治療の実際についてご講演いただきました。
関連記事
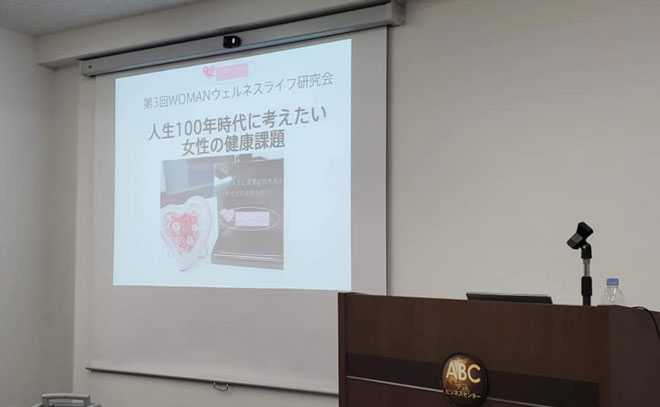
第2部は、多くの方にご協力いただき実施した「働く母1000人実態調査~健康×子育て×働き方」について概要を加倉井より報告しました。
第3部は、講演と調査報告について参加者同士で感想や課題を話し合い、発表しました。
第1部-講演「女性100年時代の健康課題 〜診療の現場から」

赤心堂病院 産婦人科医 直林 奈月氏
女性は、女性だからこその大変さを抱えている
現在、直林氏は総合病院産婦人科に勤務され、女性特有の症状や病気に悩む、あらゆる世代の女性を診察しています。受診者のうちなんと約3分の1が高齢者。女性は妊娠・出産の一時期だけでなく、長く産婦人科に診ていただくことになります。
ちなみに直林氏がなぜ産婦人科医を選んだのか。
女性は、月経・妊娠・出産・育児・女性特有の病気など、女性だからこその大変さを抱えていて、そのサポートをしたいと思ったからだそうです。こうした産婦人科医に出会えたら、とても心強いですね。
LEP/OC製剤、IUS、HRT、ペッサリー、月経カップを正しく知っていますか

実際、直林氏が「診療の現場」で出会う患者は様々。今回のご講演は、患者のモデルケースからの治療方針(あくまで一例として)をもとに、治療の実際や最新情報などをお話しいただきました。
ケース1 「イライラからの怒りで落ち込む、月経前の異様な眠気、頭痛も。(38歳)」
(診断と治療方針)月経前症候群(PMS)の疑い→LEP/OC製剤について
低容量ピルは、避妊薬(OC製剤)としてだけでなく、月経困難症の薬として治療に使われており、LEP製剤は保険適用。服用は月経関連の症状の緩和をはじめ、月経回数を減らしたり、月経周期をコントロールしたりすることができ、QOLも高くなる。女子サッカー選手だった澤穂希氏が使用していたことをオープンにした。
ケース2「月経困難が続き市販薬を多用。不正出血、腹痛、貧血の症状。(43歳)」
(診断と治療方針)子宮腺筋症→IUS(子宮内避妊システム:ミレーナ)、内服薬(ジエノゲスト)について
ISUは5年間にわたり黄体ホルモンを子宮内に放出することで子宮内膜を薄くして、月経量を減らし痛みも改善する。過多月経の治療薬として保険適用。
ジエノゲストは、副作用でいずれなくなるが不正出血はほぼ必ずおこる。喫煙者、40歳以上、肥満の方には使いやすい。ジェネリックがあるが値段はやや高い。
ケース3「月経はやや不調。発汗・イライラ・めまいなどの症状。(49歳)」
(診断と治療方針)更年期障害→サプリの使用やHRT(ホルモン補充療法)について
患者の希望にもよるが、エクオールを含むサプリをすすめたり、漢方薬を処方したりすることもある。更年期の症状は閉経前後のエストロゲンの急激な減少にあるので、HRTにより症状を緩やかにするが、日本ではHRTの治療を受けている人は非常に少ないのが現状。治療として、現在は「貼る薬」や「塗り薬」があるので使いやすくなってきている。
ケース4「陰部の違和感、排尿の障害など。(65歳)」
(診断と治療方針)骨盤臓器脱(子宮脱の場合)→ペッサリー管理、手術療法について。
加齢とともにおこりうる症状。手術が第一選択ではない。また手術法もさまざまで、再発リスクや合併症、術後の性交渉の可能性などに違いがある。ペッサリー管理は2〜4か月ごとに通院し、洗浄・交換を行う。
他にも、子宮頚がんについてもお話しいただきました。
子宮頸がんは、日本で年間約1万人が罹患し、約3000人が死亡している。20〜30歳代という若い世代が増加傾向。日本は検診受診率が諸外国と比較しても低く、妊娠してはじめて産婦人科に訪れて発見されるケースも少なくなく、子宮頸がんはマザーキラーといわれている。予防として、検診による早期発見と性交渉前のワクチン接種があるが、日本は副反応の問題などから2013年から接種勧奨されてない状況。
産婦人科医としてこれからの女性に望むこと

最後に直林氏からまとめとして「これからの女性に望むこと」として
○早めにきちんとした性教育を受ける(自分の体を知る)
○初経を迎えて、月経不順や過多月経、月経困難があるなら(なくても)、OC/LEP製剤を始める。妊娠したいときまで
○HPVワクチンを接種する
○性的同意をとってから(お互いに)
○性交渉の前にはお互いに清潔に
○妊娠したいときまではコンドームを併用(性感染症の予防のために)
○性交渉があってからは、がん検診を開始
○避妊に失敗したら緊急避妊を(処方薬あり。OTC薬化が今後の課題)
○妊娠出産後、OC/LEP製剤を再開、もしくはミレーナの使用を
○閉経前後、不正出血か月経か迷ったら婦人科受診
○その後も何かあれば婦人科へ
を挙げられていました。
講演を伺い感じたのは、女性自身が「自分の体」をまだまだよく知らないのかもしれないということです。月経関連や更年期のつらい状態をがまんしている女性は少なくありません。医療の進歩による新しい薬や治療方法を受けたり、女性用の新商品(月経カップなど)を利用したりするのも解決策の一つ。選択は自分にあるのですから。そして「つらい状態をがまんせずにまず婦人科に」ですね。
第2部-「【働く母1000人実態調査~健康×子育て×働き方】」から見えてきたこと」調査報告

「【働く母1000人実態調査~健康×子育て×働き方】」から見えてきたこと」
(株)ウェルネスライフサポート研究所 代表取締役 加倉井さおり(保健師)
実態調査のきっかけは、昨年の「週刊東洋経済」の特集:共働きサバイバルでの「悲鳴をあげる女性のからだ」というテーマで執筆依頼があった時に「働く母のデータはありませんか」という編集者の方の一言から。確かに、働く女性・母親の事例はたくさんありますが、働く母のデータはなく、それならば調べてみようと思いました。調査はインターネットリサーチで安田女子大学看護学部教授の新川治子氏にご指導ご協力をいただきました。
調査内容は、30歳代を中心に働く母親の「体」「心」「職場復帰と母乳育児」「働く母の子育て・職場と健康」「男性の働き方」についてアンケートを実施。妊娠期や育休復帰、現在など、様々なステージでの心身の状態や困りごと、サポートや職場の実際などの回答をいただきました。
見えてきたことは、
「仕事をする上で心身の不調を感じる母は8割以上」であるが「何も対処していない」という回答も多く、職場復帰後(授乳継続者のうち)乳腺トラブルの経験者は半数以上であった。また「子どもや職場に対して罪悪感、劣等感」や「不安感やつらさ」を抱えている働く母が多いという実態が明らかになった。
そんな状況の中
「仕事を辞めたい、または働き方を変えたい」と思ったことがある母は7割以上という状況。
また母の職場への満足度、パートナーの働き方の満足度が低い程、母の心身の不調を抱えているということも見えてきました。
まさに前述の雑誌掲載の記事の見出しどおり「悲鳴をあげる働く女性のからだ(&こころ)」が数字となってあらわれています。
そして自由記載欄には回答者からびっしりと書き込みがされていて、誰かに聞いてほしい、訴えたいという気持ちが溢れているのが感じられました。「一人の時間がほしい」「育児家事は手伝いでなく一緒にやるもの」など内容も切実。なかでも多く書かれていたのが「協力」「理解」という言葉でした。
調査結果は、意外というより納得というもの。しかし、働く母である当事者は当たり前ですが、周囲にはこの深刻さが理解されていません。
ただ、今は「声をあげることで変化する時代」が来ています。こうした実態を調査報告することで、社会を変えていく大きな力になるのではと感じています。ここから何ができるか、はじめるかが重要ではないでしょうか。
セミナー参加者の多くが健康支援に関わる立場でもあることから、
○妊娠、育児など時期に合わせた支援
○職場での妊娠期や育休復帰後の搾乳へ対応した環境整備をはじめ、制度、仕組みを活用するとり組み
○働く母親だけでなく、全ての人へ「女性の健康」についてのリテラシーの向上
などの必要性を挙げ、そのためには、地域支援と職場支援との両輪が必要であることを訴えてまとめとしました。
実態調査の詳細データなどは報告書として別途リリースする予定です。
第3部-意見交換

第3部は意見交換として直林氏のご講演と「働く母1000人実態調査」の報告から、参加者で「講演、調査報告を聞いて、感じたこと」「何ができるか、何から始めるか」を話し合い、発表しました。
○働く人は受診する時間もなかなかとれない。産休育休以外にも一般の働く人が健康のために取ることができる「健康休暇」があるといい。
○女性自身も自分の体をもっと知ることが大切だと思う。
○更年期の症状はがまんしない。かかりつけ婦人科医が必要だと思った。
○育休中は地域での支援を受けられるが職場復帰後は難しい状況だと思う。
○企業内に助産師がいると産休育休前後のサポートができるのでは。
○職場では育休制度はあっても男性はとりにくい。利用できる風土づくりが大切。
○働く母が相談できる人・場所がなく、孤独なのではないか、身近で相談できることが必要。
○医療の進歩における様々な新しい情報を所属に持ち帰り、活用したい。
○子宮頚がんのマザーキラーの話などを若年層に伝えたい。
○調査報告として「働く母」の気持ちを共有することで、自分一人でないと思える。多くの人に知ってもらえるようにしたい。
○職場での環境整備をすすめたい(辛いときに少し横になれるスペース、搾乳できるスペースなど)
(発表から一部抜粋)

研究会終了後も席を離れず、参加者同士で語り合うグループが多くみられ、充実したセミナーであったことが感じられました。
これから、この研究会での繋がりや気づきと学びをも活かしながら、それぞれの現場で働く女性の健康支援を推進して下さることを期待しています。
(report:Mika Masaki /photo:Kayo Kikuchi)
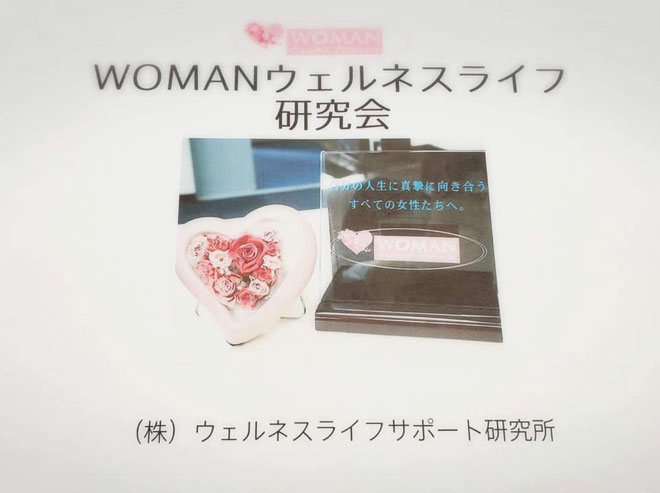
次回は第4回となり、2020年3月7日の予定です。
WOMANウェルネスライフ研究会について、詳しく知りたい方はこちらからご確認ください。
メルマガ登録のお知らせ
WOMANウェルネスプロジェクトの新しい講座・イベント情報をお送りします。